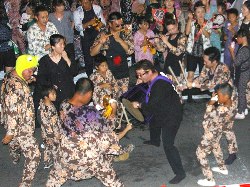Home>
青森名所巡りの旅目次>五所川原・立佞武多 2005
五所川原・立佞武多 2005
(立佞武多−平成17年「炎(ほむら)」)。
 五所川原市は津軽平野のほぼ中央に位置する。
五所川原市は津軽平野のほぼ中央に位置する。
近年立佞武多の復元で有名になり、多くの観光客を集めるようになった。
2005年の同市の「立佞武多公式ガイド」によれば、立佞武多は幕末から明治にかけて、津軽地方で散見されたらしいが、五所川原市ではっきりと記録に残ったものは、明治40年頃のもので、当時商業の中心地だった五所川原では、大地主や豪商がスポンサーとなって造らせたらしい。」
「豪商達は力の象徴として大きさ比べをしたが、電気の発達で道路に電線が張り巡らされ、立佞武多は小型化せざるを得なくなった。」
「平成5年、豪商出入りの大工の子孫が、昔の巨大ねぷたの台座の設計図(7枚)と写真1葉を発見し、翌平成8年有志達のカンパや労力提供により、約3ヶ月かけて立佞武多『武者』」が完成した。」
高さ16メートルの「武者」は、制作7日後に燃やして昇天した。
この巨大ねぷたの復活劇に刺激され、五所川原市の支援により、平成10年に立佞武多「親子の旅立ち」(高さ22メートル、重量16トン)が完成した。
市役所は、運行道路の電線を埋設したりしてインフラを整備した。」
かくして、巨大立佞武多は復活した。
平成10年以降、毎年一台づつ制作され、3年保管され、一台づつ消えていくことになった。
今年(平成17年)は、巨大立佞武多は
- 五穀豊穣−(平成15年製作−高さ22メートル、重量17トン)
- 杙(くい)−(平成16年製作−高さ22メートル、重量17トン)
- 炎(ほむら)−(平成17年製作−高さ23メートル、重量17トン)
の3台が運行され、他に中型立佞武多6台が運行された。
| (五穀豊穣−平成15年) |
(杙−平成16年) |
 |
 |
立佞武多の運行に欠かせないのが「跳人(はねと)」、「囃子方」、「踊り手」、「曳き手」などで、こちらも数多くの町の団体やサークルの団体があるらしい。
| (曳き手) |
(囃子方) |
 |
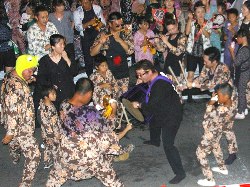 |
| (跳人(はねと)1) |
(跳人(はねと)2) |
 |
 |
立佞武多は運行コースに陣取ればどこでも見物出来るが、せっかく遠方から行くのだから、事前に購入可能な「桟敷席」の予約をお勧めする。
宿泊予定のホテルに依頼するか、ネットで申し込む。申込先は「五所川原商工会議所のHP」。
2005年の桟敷席は運行本部前に仮設したもので、高い位置から見物でき、またコンパネのベニヤに腰掛けることが出来て快適だった。
五所川原商工会議所
|
 青森の旅Top /
青森の旅Top /
 Next 五所川原の立倭武多の館
Next 五所川原の立倭武多の館 Home
Home
 五所川原市は津軽平野のほぼ中央に位置する。
五所川原市は津軽平野のほぼ中央に位置する。